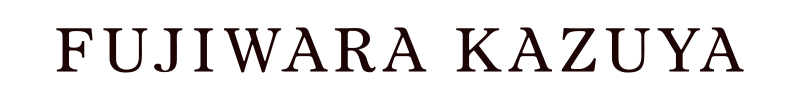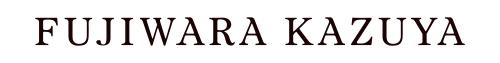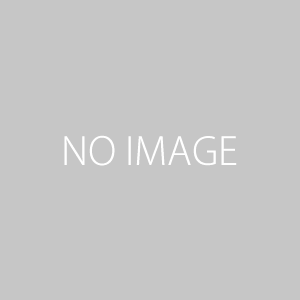冬の木(作品)
[ 写真 井上浩二氏 ]
札幌芸術の森美術館内の中庭に設置している作品「太陽のふね」(2027年4月まで設置予定です)冬の装いになりました!笑
雪の重みに耐えられるようにと思い、一本だけ支柱で支えてみました。木はタモの木を使いました。この作品の木はほとんどがカラマツなのですが、支柱はタモの木です。 結構木によって全く表情も、手触りも、匂いも、乾き方も、湿度も、棘の具合も、繊維の取れ方も、何もかも違いまして、海と川くらい違うというのが僕の印象です。特に針葉樹と広葉樹ですから全く違うのですが、年齢で言うと100000000年(!)(1億年)くらい針葉樹の方が先輩のようです。僕が木を彫りたいと思ったのは火の鳥鳳凰編という映画を見て、なんか懐かしく感じて、なんとなく始めようと思ったのですが、本格的にやってみたのは大学生からです。 なんか針葉樹って、遠いというか、神聖というか気高いというか、崇高な感じと、気難しいような、冗談が通じない時のある人みたいな、(僕も意外とそういう時がある笑)そんな感じがして、面白みがないように思う反面、急に素晴らしくなるみたいな感覚があります。 広葉樹は、、と言ってもたくさんの種類がありますが、、特にここでは栗の木とか、ニレとか、タモとかに思うことですが、すごく人と近い息遣いをしていると思っています。それはでも、僕にはなんか、近すぎて。あとなんか生活とか家具とかに使えそうな感じがして気が引けるというか、しかも成長遅いし、すごく優しい感じがします。でもなんでか苦手な感じなんです、広葉樹。上手な人むけの木というか、すごくそんな感じがしています。 ・・・長くなりましたが、言いたかったのは、作品の木はカラマツで、人類以前からあったみたいなことを思っています。そして、そんな木(作品)を見た人が、ああ、これは大事にしようか、みたいなことを思って、自分の敷地にある木を伐って柱を立てた。とかそんなことを思っていました。 古代の建物に広葉樹(縄文時代は栗の木)が使われていることが多いのには理由があって、な、なんと!石斧で木を倒すのには針葉樹は繊維が強くて無理だったのだとか!!逆に広葉樹は打撃に素直で、叩くとパラパラと剥がれるようになるので、倒しやすかったのだそう!!それは能登半島の真脇遺跡というウッドサークルの近くの博物館で実践(すごかった!!)されている研究者の方の動画があり、めちゃくちゃ面白かったです。
しかし、どうやって木って立っているのでしょうか、不思議です。根が張っていることは構造的には理解できるのですが、木の中に潜って掘っている僕としては、その木のみきの繊維の結びつきがすごく不思議。人間が立っていることもすごいですが、なんでなんで?と不思議だらけです。
さて、今年は実は展示の予定がありません。どうしようか、、作りたいものはたくさんありまして、、きっと作ると思うのですが
でもなんかもっとガラッと新しいもの、今感じていることを表すためにはどうしたらいいのだろうとか、どこでそれを見せたら良いのだろうとか、なんかモヤモヤしています。
ではまた投稿します。