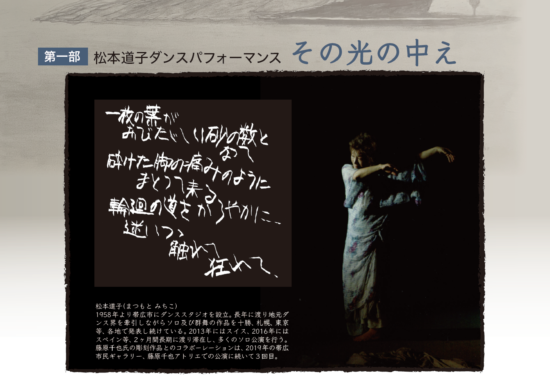冊子「美術ペン」に寄稿しました。
あけましておめでとうございます!ずいぶん更新が遅れてしまいましたが、制作は順調で楽しくてしょうがないです。樹が身体を動かしてくれる感じが本当に心地よいです。やっぱり樹はすごい。
長生きして、死んでしまう直前まで作っていたいな、なんて思っています。というよりも作ってないと生きてられないっすよね。 人間ドックで血液見たり、玄米食べるようにしたり、魚食にしたり、自重トレーニングしたり、死ぬまで彫刻をやるための準備も色々やっています。甘いもの控えるのに今は必死になっています 笑

制作中の作品です。
少し前に美術ペンという冊子に寄稿させていただきました。生い立ちと今の制作のつながりを書いてみましたので、よろしかったらご覧ください。冊子は北海道の美術館やギャラリーでお手に取れます。そうそうたる方々の文章がものすごいです。非常に面白いです。入手が難しい方のために、僕のだけで申し訳ないですがこちらに文章掲載いたしますのでご覧ください。冊子と違い、ロングバージョンですがよろしくお願いいたします。
わすれられないことがある。
「アフターダーク」という展覧会で作品展示を行い、暗い展示室でぼうっとしていると、しばらくのあいだ作品を見つめている方がいた。
「あ、この作品は……」と話しかけようと思い近づくと、その人はぽろぽろと泣き始めてしまった。話を聞くと、看護師をされており、少し前に大切に思っていた患者様を亡くされたばかりだという。作品を見ているうちに、ふいにその方のことを思い出してしまったのだと話してくれた。
あまり踏み込んで聞くのはよくないような気がして、こちらに湧いてくる問いかけの気持ちをそっと抑え、その場で会話を終えた。2021年、芸術の森美術館での出来事である。
僕は、いつもそういう出来事のすぐ隣にいた。
真駒内の丘の上にある住宅街。人目を気にするように、家の周りをびっしりと囲む木々。その内側にある、少し暗い家。山積みになった服、さまざまな物が散乱し、床をちゃんと見た記憶のない部屋。父の怒鳴り声が毎晩響き、どうしたら怒らせずに済むのか、家族全員が気を張りつめていた。いろいろな問題がいつも家族を揺らしていたが、それでもどこか、妙にあたたかかった。
その理由はたったひとつ、母の「祈り」だ。
茶の間の隣の襖を開けると、母の部屋がある。うず高く積み上げられたさまざまな物の中で、仏壇の前だけは一人分の空間がぽっかりと空いていて、そこが母の祈りの場だった。
皆が寝静まると、低い声が家中に静かに響く。小さい頃、そっと襖を開けてその背中を眺めていると、そのピンクのセーターの奥には確実に異なる世界への入り口が広がっていた。
「自分に関わる、まだ弔われていないと思われる“死”を供養し、向こうの世界へいざなうことが私の使命なの」
母はそう言いながら、三人の子どもを育て、当時の亭主関白的な価値観の渦中にいた父となんとか折り合いをつけ、毎日の祈りをひたすら続けていた。
初めはよく分からなかった僕も、家族も、やがて少しずつ、母の姿勢や、不思議なほど的中する予感めいた言葉、敬虔な態度に触れるうちに、「ああ、こういう在り方の人もいるのだ」という受け止め方に変わっていった。
こんなこともあった。ある日、学校から帰ると、母が隣の家の前で車に向かってしゃがみ込み、「うんうん、そうなのぉ、そんなこともあるのねえ」と誰かと話している。
「ああ、とうとうおかしくなってしまったのか……」と思いながら近づくと、車の下から猫が出てきた。隣の飼い猫の近況を聞いていたという。「最近エサが変わっておいしくない」とか、「新しい犬を飼おうとしていて、最近自分はあまり可愛がられていない」とか、「おばあちゃんの調子が悪くて心配だ」とか、そんなことを話していたらしい。
面白がった僕は、その猫の飼い主が友達だったこともあって、後日それとなく聞いてみた。驚いたことに、どの話題にも友達は目を丸くして「なんでそんなこと知ってんの?」と言った。
祈りは、決して明るくわかりやすいものとして受け取られてはいなかった。母の使命感は多くの人には理解しがたく、嫌悪や無理解、嘲笑の対象にもなった。見える、聞こえるという能力を利用されることもあった。長時間の祈りは、心身の不調を引き起こすことさえあった。
そんな頃、僕は映画版の『火の鳥』を見たり、お墓参りに行ったお寺で漫画版を読みふけったりしていた。木を彫る場面に強く憧れ、輪廻する世界観に、家の中で聞いていた話とのつながりを感じて、妙な親近感を覚えた。
少し後になって、ニュース映像で、廃校になった小学校でたくさんの犬たちと一緒に、アトリエで樹木を彫る人の姿を目にし、釘付けになった。砂澤ビッキさんだった。
しかし、そこから自分の作品へとつながるまでは長い時間がかかった。
木は彫れば彫るほど小さくなる。そのことが何よりも嫌だった。この樹が生きてきた時空まで縮小し、無理やり僕という小さな世界のスケールに引きずり込んでしまっているように思えたのだ。
それでも一方で、彫りたくて、どうしようもなく彫りたかった。学生時代には、大きな木をほとんどなくなるまで削り取ってしまったこともある。「お前は造形的なセンスがないから、早く北海道に戻って違うことをしたほうがいい」と、大学の先生に真剣に諭されたこともあった。今では、その教授の気持ちもよく分かる。
卒業後、多くの友人たちは大学に残ったり、別の仕事に就いたりしていたが、僕は知り合いに誘われるまま高野山の森林組合に入った。宗教と森林が同時に存在する場所に、自分の求めている何かがあるのではないかと思ったのだ。
はじめのうちは、木を切ることが嫌でたまらなかった。どうしてこんなにも精一杯生きているものを、切らなければいけないのかとためらった。しかし、日々の仕事を終えるたびに、間伐をしたあと、光をさんさんと浴びて森が息を吹き返していく様子に気がつくようになった。
その後、制作場所と樹を求めて北海道に戻り、制作を続けたが、やはり樹と一つになれない自分がいた。
木の中に潜り込むようにして掘ろうと思ったのは、そんな不器用な僕の、最後の手段だったのかもしれない。そしてそこには、僕が求めていたすべてがあった。
頭にライトをつけ、チェーンソーを持って横ばいになり、少しずつ中を掘り進めていく。硬い木では、一日に二十センチも進まないこともある。それでも、最高の時間だった。
とうとう樹と友達以上のなにかになれたかもしれない――そう思えた。
小さい頃、砂場に掘ったトンネルの両側から手を伸ばして握手したとき、世界中の人とつながれたような気がしたこと。母のスカートの中に潜り込んだとき、全ての生命とつながったように歓喜したこと。食卓の下にもぐると、家族の気配を全身で感じて安堵したこと。マンホールに耳を当てると、まるで別世界のような美しい水の音が聞こえたこと――。
あのとき感じていた「どこか別の世界へ通じる穴」が、木の中の空洞と重なっていった。
硬い枝の部分を掘ると、そこはぴかぴかと光り、その木理は宇宙の始まりのようだった。旋回する木目は、一つの場所で生きることを宿命づけられたこの樹が、風を受け続け、かわし続けてきた証だ。年輪として同心円状に刻まれた線は、この樹が星の運行を覚えているかのようにも見える。
樹の中は、光の記憶にあふれていた。
見えていなかった光を、もし「魂」と呼んでよいのなら、ここに魂はある。
全ての魂が人知れず、この光を内側にそっと持ち続けている。
生まれようとした時、私たちは何を願ったか
私はそのように生きているか
今はそっと、ひとつ一つの「魂」という光を沢山の人と見ることで、少しでも世界の平和や希望に役立てればと願っている
2025.12.1 彫刻家 藤原千也
読んでいただいた方ありがとうございます!!! それではまた、、!!!